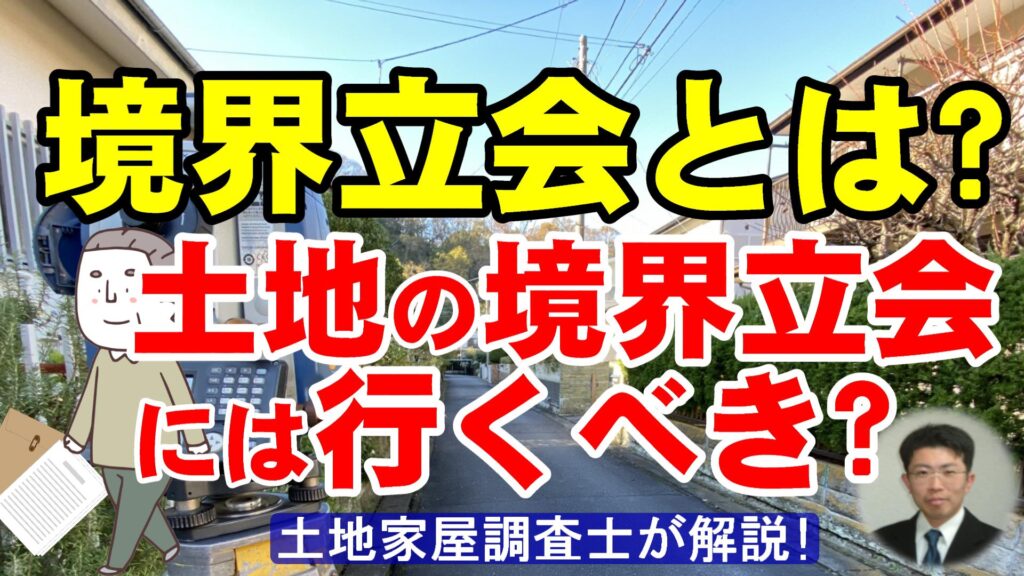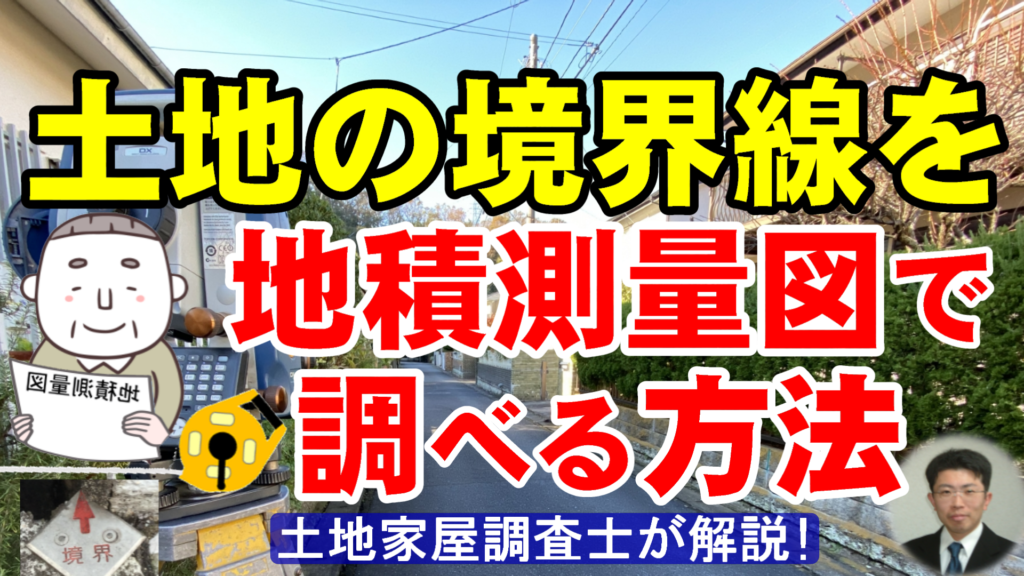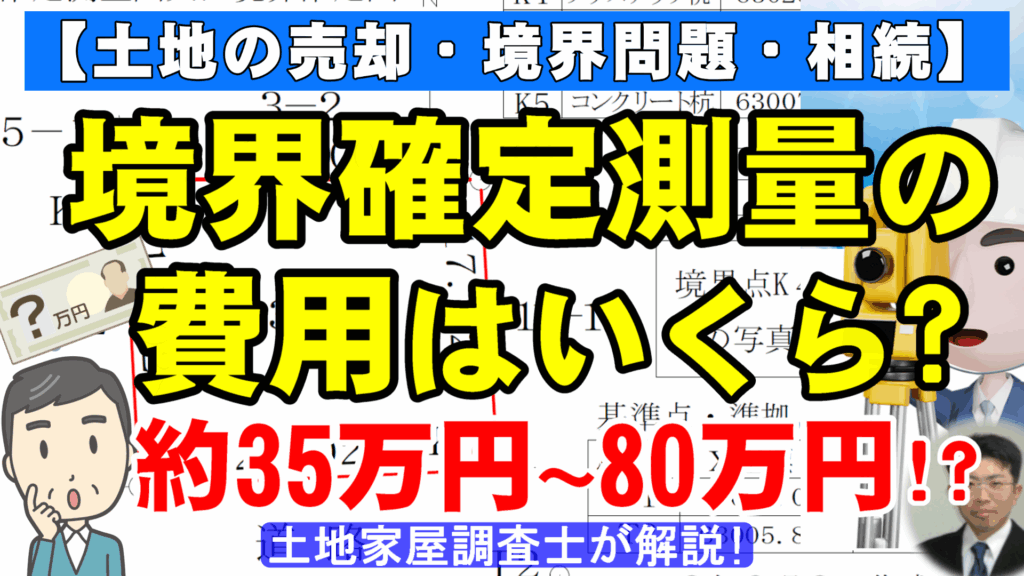土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。
経歴:開業以来23年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら
「隣の家との境目が分からない」
「いつの間にか境界標がなくなってしまった」
もし、あなたがこのような悩みを抱えているなら、
隣人トラブルに発展する前に、この記事が解決の糸口になります。
この記事では、土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が、
専門家でなくても境界線を特定できる3つの具体的な方法と、
知っておくべき法的知識を徹底解説いたします。
このまま放置すれば、後悔する事態になるかもしれませんので、
ぜひ最後までご覧いただき、
あなたの財産と安心を守るための第一歩を踏み出してください。
この記事を全て読む事で、隣地トラブルに巻き込まれることなく、
ご自身の財産を適切に管理するための確かな一歩を踏み出すことができるでしょう。
【この記事の内容を動画で見る】
この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。
記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
境界標がない!探す前に知っておきたい意外な事実とは?
境界標が見つからない場合、
ご不安に感じられる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、境界標が見当たらない意外な事実を明らかにし、
適切な対応をスムーズに進められるように、
あらかじめ知っておくべき点をお伝えします。
なぜか見つからない境界標…その原因は?
一生懸命探しても見つからない境界標は、
単純に見落としているだけということもありますが、
最初から無かったり、土や砂利の中に埋もれている可能性もあります。
もし、以前、境界標が設置されていても、
隣接する道路や里道(農道)の工事、又は水路の工事、
あるいは隣接地の外構工事などにより、撤去されてしまった可能性もあります。
また、境界標は、土地の全境界点に設置されている訳ではなく、
全境界点に境界標を設置している土地もあれば、
一部の境界点にのみ境界標を設置している土地もあり、
元々、境界標がまったく設置されていない土地もあるのです。
もし、元々境界標が設置されていなければ、
いくら境界標を探しても、見つかるはずもないのです。
また、境界標が土砂などの中に埋もれている場合には、
見える範囲をいくら探しても、見つかるはずもありません。
だからと言って、境界付近の土砂などを全て掘るというのも、
大変な労力がかかり、結局、境界標は見つからない可能性もあります。
そもそも「境界標」とは何か?
境界標とは何か、どのような種類があるのか、
基礎知識を理解することで、なぜそれが見つからないのか、
あるいは何を探すべきなのかが明確になります。
そこで、境界標の基本的な知識について、簡単に解説致します。
境界標は、土地の所有者間で合意された境界を示す重要な目印です。
ただ、境界標と言えるのは、次のような金属標、金属鋲、
コンクリート杭、プラスチック杭、石杭の5種類が一般的です。
なお、木杭や、コンクリートなどへの刻印が、
境界標としての役割をしている場合もあります。
境界標は、通常、土地の所有者からの指定が特に無ければ、
土地家屋調査士が、各境界点の状態などから判断して、
最適な境界標を設置しています。
例えば、コンクリート上に境界標を設置する場合には、
通常、金属標か、金属鋲のどちらかを選択して設置します。
土や砂利の所に境界標を設置する場合には、
通常、コンクリート杭か、プラスチック杭、
石杭のいずれかを選択して設置します。
そのため、境界標として探すべきは、金属標や、金属鋲、
コンクリート杭、プラスチック杭、石杭のいずれかになるのです。
ただ、以前までは、境界標が設置されていたとしても、
長い年月の間に、道路工事又は水路工事、
若しくは外構工事が行われ、その時に境界標が撤去されてしまい、
誰も気づかず、撤去されたままといったこともよくあります。
そのため、境界標を現地で探す際には、過去に、
境界付近で何らかの工事がされていないかどうか、
といった視点で現地を見て、境界標を探すことも大事なのです。
また、以前の土地所有者が、境界を厳密に定めていなかった場合、
そもそも現地に境界標が設置されていないケースも、
決して珍しいことではないことを知っておくことも重要です。
最初にやるべきは「探すこと」ではない?
多くの方が、現地で境界標を探すことから始めますが、
実はその前に確認すべきことがあります。
この記事で解説する「3つの方法」は、この「探す前の準備」から始まります。
なぜなら、先に準備をする事で、その後の調査がスムーズになり、
より正確な情報を得られるからです。
土地の境界線を調べる3つの方法と注意点
土地の境界線を調べるには、次の3つの方法があります。
- 方法1:法務局や市区町村役所で資料を調べる。
- 方法2:境界に関する資料と照らし合わせながら、現地を調べる。
- 方法3:土地家屋調査士に依頼する。
それでは、これら3つの方法を順番に解説いたします。
方法1:法務局や市区町村役所で資料を調べる。
まず、法務局で、下図のような土地の地積測量図と公図、
登記簿謄本などの登記情報を取得します。
地積測量図というのは、土地を測量した際の図面で、
境界点の位置や、境界標の種類などが記載されているので、
境界に関する重要な資料となります。
ただし、地積測量図については、
全ての土地に必ずあるわけではありません。
地積測量図が法務局に提出されていない土地も多々あるため、
地積測量図が無い場合は、公図が境界に関する資料になります。
公図では、周囲の土地との位置関係がわかり、
登記簿謄本などの登記情報では、
土地の面積や所有者の住所と氏名の確認ができます。
なお、地積測量図や公図によっては、
現地と完全に一致しない場合もあるため、
あくまで、境界に関する資料と認識しておく必要があります。
また、市区町村などが管理している里道(農道)や水路、
又は国道や県道、若しくは市区町村道と接している場合には、
市区町村役所の担当課で、境界に関する資料の有無を調べて、
もしあれば、それら境界に関する資料も取得します。
なぜなら、法務局に地積測量図が備わっていない場合でも、
土地に接している里道(農道)や水路、道路との境界確定資料が、
市区町村役所で保管されている場合もあるからです。
もし、過去に地籍調査事業や区画整理事業が行われていれば、
測量図などの境界に関する資料が、通常、
市区町村役所の担当課で管理されているので、
それらの境界に関する資料も取得します。
方法2:境界に関する資料と照らし合わせながら、現地を調べる。
下図のような土地の地積測量図を入手できれば、
まず、境界標の種類の記載があるかどうかを確認します。
もし、地積測量図に境界標の種類の記載があれば、
どの境界点に、どんな境界標があるのかを確認するのです。
たとえば、境界標として金属鋲と記載されていれば、
少なくとも、その地積測量図を作成した当時は、
現地のその境界点に、金属鋲が設置されていたということになります。
そのため、その境界点の境界標を現地で探す際には、
境界付近にある金属鋲を、重点的に探せば良いということになるのです。
境界標の種類の記載が、金属標やコンクリート杭でも、
プラスチック杭や石杭でも、同じことです。
逆に、地積測量図など境界に関する資料が何もない状態だと、
金属鋲なのか、金属標なのか、プラスチック杭なのかわからず、
境界標があるのかどうかすらわからずに、探し回ることになってしまいます。
なお、地積測量図に限らず、役所が管理する里道(農道)や水路、
道路との境界確定図面などを、役所で入手できれば、
同じ作業を行って、現地で境界標を探す流れになります。
つまり、地積測量図などの境界に関する資料があり、
その地積測量図などの資料に境界標の記載があれば、
境界点のある位置や、どんな境界標があるのかも、
ある程度わかった上で、境界標を探すことができるのです。
現地で境界標を探す際には、地積測量図等と照らし合わせて、
現地に残っている他の境界標や基準点から、
探したい境界点までの距離を、スケールや巻尺などで確認し、
現地で境界標を探すと、比較的見つけやすくなります。
ただし、地積測量図などの境界に関する資料があっても、
全ての境界点に境界標が設置されているわけではないため、
境界標の記載が無い場合もあります。
その場合には、復元測量や、隣地所有者と境界立会いを行って、
境界を確認する方法がありますが、根拠は何かなどの問題や、
隣地所有者とトラブルになりかねないので、
お近くの土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。
なお、地積測量図など境界に関する資料から、
土地の境界線を確認する具体的な方法については、
「土地の境界線を確認する方法を解説!」で、
くわしく解説しています。
方法3:土地家屋調査士に依頼する。
境界標を探したり、境界標を現地に元通り復元する作業や、
境界標を設置したい場合には、土地家屋調査士に依頼するのが、
最も確実で、安全な方法となります。
なぜなら、土地家屋調査士は、境界に関する専門知識と、
測量技術を備えており、境界標を探したり、境界標を復元したり、
境界標の設置など、境界確定作業全般を行っている専門家だからです。
たとえば、下図のようなXY座標による地積測量図がある場合、
土地家屋調査士であれば、測量機器を用いて復元測量を行い、
ピンポイントで境界点を現地に落として、
境界標の有無を探し出すことができます。
また、隣地所有者と現地で境界の確認をする際にも、
土地家屋調査士なら、第三者の専門家としての公平な立場で、
地積測量図などの境界に関する資料を根拠にして、
お互い納得できる説明を行うこともできるのです。
もし、隣地が里道(農道)や水路、道路など、
公的な土地であれば、境界の立会いに来てもらうためにも、
境界立会い申請書類といった手続き書類を作成して、
役所に提出する必要があり、それらの手続きも任せることができます。
ただ、土地家屋調査士に依頼する場合には、
費用が発生するため、事前に見積もりを取ってから、
依頼することをお勧めします。
境界標の紛失や不明のまま放置するのはトラブルの原因?
境界標が無い状態を放置していると、将来的に、
次のような深刻なトラブルに発展する可能性があります。
- 越境トラブル
- 売却時のトラブル
- 相続時のトラブル
それぞれ具体的にどのようなトラブルなのか、簡潔にご紹介いたします。
越境トラブル
具体的には、隣地との境界が不明確な場合、
フェンス又はブロック塀を設置したり、建物を建てる際に、
意図せず隣地を越境してしまい、トラブルになることがあります。
売却時のトラブル
土地を売却する際に、境界が明確でないと、
買い手が見つかりにくくなったり、
価格交渉で不利になることがあります。
また、境界が明確でないまま売却した場合、
売却してからも、境界トラブルに巻き込まれる可能性があります。
相続時のトラブル
相続の際に、相続人同士で境界を巡って意見が対立し、
争いの原因になることがあります。
土地家屋調査士への依頼の方法
まずは、お近くの土地家屋調査士事務所に電話、又は来所して、
相談や依頼をするという流れが一般的です。
もし、相談だけの場合には、初回無料の所もありますが、
30分あたり3,000円~4,000円程度が相談料の目安となり、
依頼の場合には、土地家屋調査士事務所によって、
料金が異なっているので注意が必要です。
以上、「境界標が見当たらない!
境界線を調べる3つの方法と法的知識」について解説いたしました。
なお、当所でも、お電話によるご相談などを、
YouTubeチャンネルで、メンバーシップ特典として、
常時受付けております。
面談に行く時間がなかなか取れない方や、
誰に相談すれば良いのかわからないという方は、
当所のYouTubeチャンネルのメンバーシップの特典を、
1回(1ヶ月)だけご活用いただく方法もございます。
また、土地の境界線を調べる作業を、
土地家屋調査士に依頼した場合、
費用がいくら位かかるのかについては、
「土地の境界線を調べる費用はいくら位?」をご確認下さい。
地積測量図で、土地の境界線を調べる方法については、
「土地の境界線を地積測量図で調べる方法」で、
具体的にくわしく解説しています。
土地の境界線を確認する方法については、
「土地の境界線を確認する方法を解説!」をご参照下さい。